代理権不消滅(合併&代取交替)による抵当権抹消
飛び込みのお客様から日本総合信用株式会社の抵当権抹消のご依頼です。
「ニッソウシン」って言ってました。なつかしいです。
クオークの放棄証書(抵当権設定契約書に奥書形式)と委任状を持参されました。ああこれは代理権不消滅だとピンときますね。
代理権不消滅は平成5年の不動産登記法改正で新設された規定です。
(代理権の不消滅)
- 第17条
- 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
- 本人の死亡
- 本人である法人の合併による消滅
- 本人である受託者の信託に関する任務の終了
- 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
民法111条と653条の例外規定です。
(代理権の消滅事由)
- 第111条
- 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
- 一 本人の死亡
- 二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
- 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
(委任の終了事由)
- 第653条
-
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
- 一 委任者又は受任者の死亡
- 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
- 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
わたくし意外と几帳面でこんな風にファイルで資料を整理してました。
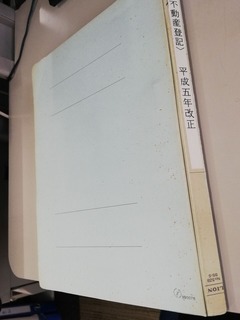
私は代理権不消滅の規定がある以上、合併承継会社は登記義務を承継しないと考えました。
調べてみましたが合併の代理権不消滅の書式が出てきません。そこで下記記載でいいか法務局に照会をかけました。
義務者 本店・・ 消滅会社の委任時の本店
商号・・ 消滅会社の委任時の商号
代表取締役・・ 委任状記載の代表取締役
(合併消滅時の代表取締役・・ )
会社法人等番号 消滅会社の会社法人等番号
その他の事項(登記義務者の代表取締役・・の代表権限は消滅している。代表権限を有していた時期は・・~・・である)
法務局から電話がかかってきました。
登記官「そもそもそんな登記できないですよ」
私「えっ?2号と4号を重ねて適用できるのでは」
登記官「できるというなら根拠を送ってください」
私「・・・はい」
条文を送るのか??と思っていたら電話がかかってきました。
登記官「できます」
「義務者のところは合併承継会社の記載が必要です」
私「代理権不消滅なので合併会社は登記義務を承継してないと思うのですが・・」
登記官「登記義務の承継という意味ではないですが記載してください」
ここが釈然としませんでしたが、この申請人が誰になるのかは後で記載しますね。もう一つ教訓もありますし。
とりあえずここで申請書の記載を紹介しておきます。
義 務 者 (被合併会社 株式会社クオーク)
(会社法人等番号 0104-01-065100)
代表取締役 仁瓶 眞平
名古屋市中区丸の内三丁目23番20号
承継会社 SMBCファイナンスサービス株式会社
(会社法人等番号 1800-01-070519)
代表取締役 小野 直樹
添付書類
登記原因証明情報 合併証明書 変更証明書 登記済証
代理権限証明情報 会社法人等番号 閉鎖事項証明書
その他の事項
登記義務者(被合併会社)の代表取締役仁瓶眞平の代理権限は消滅している。
代理権限を有していた時期は、平成15年6月25日から平成21年4月1日である。
登記はとうに完了していますからこの記載でOKということです。
さて釈然としなかった登記申請人の問題です。合併は個人の死亡とパラレルに考えることができます。下記先例がありました。相続証明書を添付するとあります。
登記申請の代理権が消滅していない場合の申請書の添付書類等について(平成6年1月14日付け法務省民三第366号通知)
(照会)
標記については、本年7月30日付け法務省民三第5320号民事局長通達(以下「基本通達」という。)の記の第二で示されているところでありますが、下記のとおり取り扱って差し支えないものと考えますが、いささか疑義がありますので、照会いたします。
記
1 登記名義人が登記申請の委任をした後死亡した場合において、相続人がその委任を受けた代理人により当該委任に係る代理権限証書を添付して登記の申請をするとき
(1)当該申請が不動産登記法施行細則(以下「細則」という。)第42条第1項又は第42条ノ2第1項の適用を受けるものである場合には、申請書に、相続を証する書面のほか、登記名義人の印鑑証明書(作成後3か月以内のものに限る。)の添付をも要する。
(2)当該申請が不動産登記法第44条の規定による保証書を添付してするものであり、かつ、保証書の登記義務者の表示が死亡した登記名義人となっている場合には、登記申請人である相続人全員あて同法第44条ノ2第1項の規定による通知をするものとし、これに対し、相続人全員から印鑑証明書を添付して同法第44条ノ2第2項の規定による申出があったときは、申請を受理して差し支えない。
2 登記申請の委任をした法人代表者の代表権限が消滅した場合において、その委任を受けた代理人が当該委任に係る代理権限証書を添付して登記の申請をするとき
(1)申請書に添付された登記申請の代理権限を証する書面の作成名義人である法人の代表者が現在の代表者でない場合には、当該代表者の代表権限を証する書面として申請書に添付する書面には、当該代表者が代表権限を有していたことを明らかにする当該法人の閉鎖登記簿謄本が含まれる。この場合において、閉鎖登記簿謄本は、作成後3か月を超えるものであっても差し支えない。
なお、上記のような書面を添付して申請をするときは、その代理人において当該代表者の代表権限が消滅している旨を明らかにする必要がある。
(2)商業登記等事務取扱手続準則第9条第2項の規定により登記用紙の末尾に閉鎖した役員欄の用紙が編綴されている場合には、基本通達第二の1のアの「当該法人の登記簿」は、この閉鎖した役員欄の用紙を含むものとして取り扱う。
(3)基本通達第二の1のなお書きについては、当該代表者の印鑑について商業登記規則第九条ノ二の規定による処理がされた印鑑紙が保存されているときであっても、印鑑証明書の提出を要する。
(回答)
いずれも貴見のとおり取り扱って差し支えないものと考えます。
この先例の詳しい解説が登記研究556号(平成6年5月)「訓令・通達・回答」≪5100≫にありました!登記研究も本を割いてファイリングしなおしてます(めんどくさすぎて今は登記研究自体取っていません💦)
「なお、本通知が相続を証する書面の添付を必要としているのは、代理権不消滅の規定であっても、登記の申請人となるべき者は死亡した登記名義人ではなく相続人であるから、法42条により相続を証する書面の添付が必要とされたためであり」と解説されています。
「登記の申請人となるべき者は死亡した登記名義人ではなく相続人である」ということです。
合併の場合は、合併承継会社が申請人ということですね。申請書に承継会社をも記載し、合併証明書を添付することになります。
司法書士に委任状を渡しても登記申請が完了していない以上、登記申請義務を履行しきったとは言えないのでしょう。
登記完了後も釈然としなかったのがこの解説を読んですっきりしました。やはりファイリング大切です。
さて、教訓です。
日本総合信用は、商号変更、合併、本店移転、会社分割等と複雑な経緯をたどっています。大阪司法書士会発行のありがたい「金融機関等変遷便覧」でも経緯が判然としません。SMBCファイナンスサービス株式会社に問い合わせたところ書類の発行手数料として「5500円」かかるといわれました💦
5500円はもったいない、依頼人の負担が増えると代理権不消滅を使うことにしました。
ところが合併、本店移転、商号変更を同日付でしてるんです。私も本店移転と商号変更を同日でとか、同日付の依頼を受けますが、依頼するお客様は何気でもこちらはプロです。後で経緯を辿れなくならないように申請順を考えます。が、この会社は経緯を辿りにくい順番で登記申請されていたのでしょう。オンラインの履歴事項2通、郵送申請の閉鎖謄本2通取り寄せても完璧にはつながりませんでした。(欄外に変更後の商号が記載してあったので登記は通りましたが)。
ここは「5500円」払って再発行を受けるべきでした。繋がりのつく登記事項証明書をぜんぶ用意してくれるはずですから。
この方、もう一件住宅金融公庫の抵当権抹消の書類も持参されていました。(紛失されなかったのはご立派です)
住宅金融公庫から住宅金融支援機構は合併ではないので代理権不消滅の規定は使えないです。こちらは再発行手数料は不要でしたが、再発行請求にご本人の印鑑証明書と不動産の登記事項証明書原本が必要でした。
私は、通常、抵当権抹消1件を実費込みで2万円弱でしていますが、今回は2件で5万円になりました。報酬は37700円です。聞いてたより高いと苦情を言われましたが、いや、ものすごく、ものすごく面倒でした![]()
どうか、何十年も放置しないでその都度登記申請をしてください。圧倒的に簡単で安いですから。
(令和4年9月)
